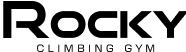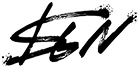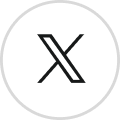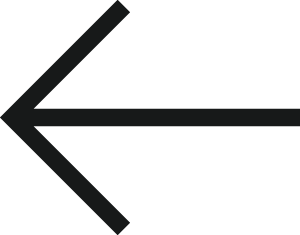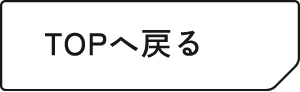2025-11-11
石を巡る物語 (第一回「石の人」と「静かの海」)
文:室井登喜男
本誌の発刊にあたって、編集部から依頼された内容は、これまで初登した課題を毎回1本取り上げて、それにまつわる話を書いて欲しい、というものだった。快く承諾したものの、単に私が思い出話を語るようなものでは、若い読者にはいささか退屈だろう。そこで、日本のボルダリング史などを振り返りつつ、その中で自身とその課題について語ってみたいと思う。時代が多少前後するので、やや分かり難いかもしれないが、よろしくお付き合い頂きたい。
始まりと革新
まずは、一般的に言われる日本のボルダリング史について振り返ってみよう。日本のボルダリングは、70年代末から80年代初め頃の、王子ヶ岳や北山公園でのクライミングが、その始まりと言われる。関東では、やはり同時期の鷹取山あたりが始まりとされ、小川山や御岳は、少し遅れた82年から登られている。
しかし、今日のようなスポートルート、トラッドルートといったジャンル分けの感覚でこれを見ると、当時のクライミングシーンを捉えにくい。その頃は、今のような確立したスタイルやジャンル分けはなく、フリークライミングというもっと大きな枠でクライミング全体が捉えられていたし、「ボルダラー」などという言葉も、耳にすることはなかった。
実際、一部のボルダーはトップロープで登られていて、時にトップローププロブレムなどと呼ばれることもあった。どこまでがボルダーで、どこまでがルートなのか、今の視点で見ると、かなり曖昧としている。やや乱暴だが、見た目が「壁」ではなく、スケールに関わらず「石」と言えそうな形状の岩を「ボルダー」と呼んでいた、と言えるかもしれない。実際、辞書的に捉えれば、ボルダーという言葉は、本来は巨石、玉石といった意味なので、それも納得がいく。
今のようなボルダリングのスタイルが確立するのは、それから10年後の90年代初めであり、その立役者が草野俊達氏である。
アメリカでジョン・ギルの課題を訪ねるなどして、90年代からボルダリングに傾倒していった氏は、日本でも新時代の課題を各地で初登し、それを95年の「岩と雪」169号に「石の人」という文として発表した。
この「石の人」に掲載された課題は、スタイルとしても、グレードとしても、日本のボルダリングに新たな時代の訪れを告げるような革新的なものだった。また氏が考案し、現在のスタンダードである段級グレードも、ここで初めて付されている。課題の紹介のみならず、少ない言葉でボルダリングのエッセンスを語る氏の文は、一部のクライマーからは熱狂的に支持された。
同じものと違うもの
かなり駆け足で紹介したが、以上が日本のボルダリング史の黎明期として一般的に言われている話だ。このように振り返ると、グレードやスタイルなど、日本でボルダリングが一つのジャンルとして確立し、大きく発展したのは90年前半からと言える。ただし、注意してもらいたいのは、「90年代から始まった」ではない点だ。「90年代から・・・」と語られることが多いので、うっかりすると勘違いしそうだが、ボルダリングそのものは、70年代末からある。
この部分の歴史の捉え方は、なかなか難しい。筆者も当事者として、90年代以前に行われていたものは、現在とは何かが違った感じがするし、クライマーの意識も今とは違ったと感じる。菊地敏之氏が日本のクライミング史についてまとめた著書「我々はいかに『石』にかじりついてきたか」には、初期の鷹取山でのボルダリングについて「我々のそれをもってボルダリングの先駆とするのは、きょう日いささか気が引ける」とあるし、90年代の話として「ボルダリングなんてものはイムジン河とか登った夕方に、ボルダリングでもすべえか、って感じでやるもので、そんなボルダーボルダーなんて大騒ぎするもんじゃねえよ」とある。その後はともかく、当時の多くのクライマーの認識を的確に代弁しているように思える。
それでも70年代末~80年代初めに各地で行われていたものは、では何だ?と聞かれれば、やはりボルダリングと答える他ない。そもそも、ボルダリングはシューズとチョークだけでただ岩を登るという、最もシンプルかつプリミティブなクライミングなのだから、部分的な違いはあっても、本質的には違いを見出しようがない。
筆者は日本のボルダリング史を語るときに、いつもこの部分にモヤモヤとしたものを感じている。90年代の前と後では、何かしらの違いを感じるのだが、しかし、「何が違うんですか?」と聞かれれば、「本質的には同じです」としか言いようがない。「90年代から盛んになった」と言ってみても、90年代以前には、フリークライミングという大きな枠の中で渾然となっていたのだから、どうも的確でない気もする。
しかし、変わりようがないシンプルなスタイルでありながら、何か大きな変化を感じることもできるのが、ボルダリングの奥深さであり、醍醐味とも言えるだろう。そう思えば、この先にも新たな時代が来る可能性があるのだから、なかなかワクワクする話ではないか。
「石の人」と小川山
さて、少し逸れてしまったので、90年代からのボルダリング史に話を戻そう。先に「石の人」が熱狂的に支持されたと書いたが、しかし、それは例えば、瑞牆が発表されたときのように、多くのボルダラーが押し寄せるというような状態ではない。そもそものクライマー人口が、今とは比較にならないくらい少なかったこともあるし、ボルダリング自体に目的や目標を見出すクライマーは極めて稀だった。当時の主流は圧倒的にルート、それもスポートルート全盛期であり、「石の人」のそれは一部を除いて、ややマニアックなクライミングとして捉えられていた感すらある。
筆者はまさに、その一部の熱狂的なクライマーの一人であり、「石の人」に大きな衝撃を受けた。新時代のボルダリングにすっかり魅了されて、時に仲間と、時に一人で草野氏の課題を登りに出かけ、行った先では、いつも同じ限られた面子と顔を合わせるといった調子だった。なかでも小川山は、スポートクライミング全盛期にあっては、そもそも訪れるクライマーが少なく、一日誰とも会わないことも珍しくなかった。
その「石の人」の小川山の部分を読むと、今日ではいささか困惑を覚えるだろう。書き出しには「小川山にあるボルダーは本当に少し、10個くらいしかない。でもなかなかいい」とあり、掲載されているのは合計6課題しかない。現在の小川山のボルダーの有様を考えると、とても同じ場所について述べているようには思えない。意味不明に思えるだろうが、しかし、当時としては、「小川山はボルダーが少ない」という認識が一般的だったし、多くのクライマーにとって、小川山=ルートの岩場という認識が支配的だった。いかに当時はボルダーに目が向けられていなかったかが分かるだろう。
そんな中にあって、熱に浮かされたように小川山に通い詰め、眠れる小川山のボルダーを手当たり次第に掘り起こしたのは、他ならぬ筆者である。草野氏の課題を登る傍ら、小川山じゅうを歩き回って「石楠花遊歩道」「親指岩下」「屋根岩」「水晶スラブ下」といったエリア単位の開拓をして、岩をしゃぶり尽くすようにラインを引いて行った。その集大成は「小川山、御岳、三峰ボルダー図集」としてまとるのだが、その話はまた別の機会に譲ろう。
小川山 廻り目平キャンプ場より

「静かの海」
さて、そんな怒涛の小川山開拓の中にあって、筆者が一際目を引かれたのが、今回取り上げる「静かの海」である。「静かの海」がある「水晶スラブ下エリア」は、当時まったくの手つかずだったのだから、今にして思えば何とも贅沢な開拓だ。そのエリアにあって、一際美しく、一見して目を引くのは、やはり「不可能スラブ」の岩だろう。そして、その岩の中で、真っ先に可能性が見出せるのが、「静かの海」のラインである。
トライを始めたのが94年の秋と記憶しているが、何しろ当時は日本初の三段である「蟹」が、草野氏によって登られたばかりの時代である。日本全体でも、今とは比べものにならないくらいボルダラーのグレードレベルは低く、筆者とて例外ではない。トライを始めた当初、「本当にこれは人が登れるラインなのだろうか・・・」などという思いが過ぎったことを記憶している。
94年秋には数日ほどトライするものの、リップを取ったところからサッパリ進めず、あまり可能性が見えなかったこともあって、本格的なトライはしなかった。そもそも、他にも登りたい岩が山ほどあったのだから、1つの課題に打ち込んでいる場合ではなく、エリアに行ったときに、ちょっとトライするという程度だった。
それでも、いつもどこか頭の片隅に、そのラインのことがある。「あの美しい岩を登れたら、突破口を開くことができたら、どれほど素晴らしいだろうか・・・」そんな思いが、頭から離れない。トライすれば打ちのめされて、「もうやめだ!」と思うのに、やはり離れないのだ。
95年になり、前年とは変わって本格的なトライを開始する。まだまだ登りたい岩は沢山あったのだが、やはりどうしてもこのラインが登りたい、この岩に突破口を開きたい、そんな思いに駆られて、秋のベストシーズンを狙って、1本集中型のトライを重ねた。
その年には、リップの先の凹みを左手で捉え、ようやく上部のスラブに顔を出すことができた。しかし、スラブを見渡しても右手は僅かな皺くらいしか見えない。その皺を捉えても、まったく体を引き上げることができず、そのままその年は終わった。依然として「登りたい」という思いと、「本当に登れるのか」という思いが、頭の中で回っていた。
迎えた96年。トライを始めた頃に比べれば、いくつもの段課題を登り、実力も自信もついた。何とかして登ってやろうという思いを抱いて、前年同様、秋に1本集中型のトライを重ねた。前年には頼りなかった右手の皺をしっかり保持し、力づくで左足を上げていく。当時の筆者としては、マックスのパワーを出したと言っていいだろう。
そうしたトライを数日重ね、ついに左足をリップの上に置くことができた。後は持ち前の柔軟性を活かして、左足に力を入れて立ち上がっていく。一時は不可能とさえ思った岩を足下にした時、自分の中で何かが大きく変わるのを感じた。そして、それは当時は想像もしていなかった、その後の長きに渡る、この不可能スラブとの格闘の幕開けでもあった。こうして96年の10月に「静かの海」は完成した。
静かの海を登る室井登喜男

課題を巡る物語
今回、撮影にあたって、久々に「静かの海」を再登した。12月の小川山は寒く、体調も優れなかったが、それでも割とアッサリと再登することができた。今日、このラインを見て「不可能では?」と思う人は少ないだろうし、自分でもなぜこれほどまで苦労したのかと思いもする。しかし、当時のことに思いを馳せれば、それも理解できる。
今日のようなボルダリングの確立がなく、ほとんど人のいない小川山のボルダー。まったく手つかずで、突破口の開かれていない厳しい岩。そして、自身にとって経験したことがないような難しさと、その高難度への初登をかけた挑戦。すべてが未知の世界だったのだから、当時は何よりも困難であっただろう。この初登を皮切りに、筆者は数多くの高難度課題を初登することができた。「静かの海」は、筆者にとって新たな扉を開くことだったのだろう。
最後に一つだけ付け加えておかなくてはならないことがある。「静かの海」は近年、リップ上の凹みがチッピングされたと言われている。今回再登してみても、それが本当にチッピングなのか、真相は分からないが、確かに凹みが以前よりもしっかり掛るような感触を覚えた。極めて残念なことだが、「静かの海」は初登時とは、その姿が変わってしまっている。
チッピングされた課題をどう考えるかは様々な意見があり、難しい問題だろう。筆者もなかなかその答えは出せない。ただ、改めて登ってみても、やはり素晴らしい課題だと感じたし、姿は変わっても登ってもらいたいとも思う。そして、もし仮にチッピングした当人が本文を読むのなら、課題にはどんな物語があるのかを知ってもらいたい。そういう思いで、今回は「静かの海」を取り上げた。
(続く)
静かの海がある不可能スラブ

参考文献
山と渓谷社「岩と雪」169 号
東京新聞出版社「我々はいかに『石』にかじりついてきたか」菊 地敏之